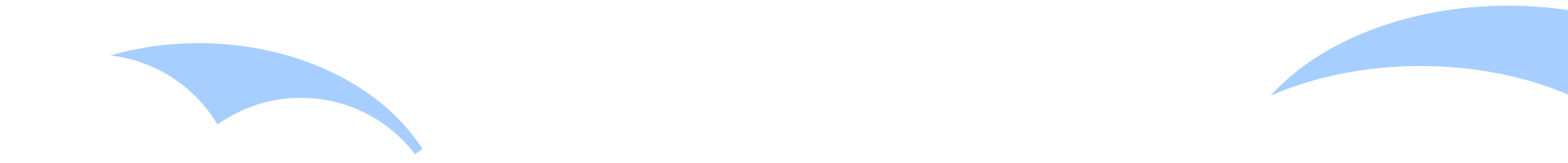砂利の敷均しと転圧
おや?土を耕して野菜でも作るのでしょうか。
いいえ、土を耕しているわけではありません、函渠の中に砂利を敷均しているのです。
砂利を敷き均したら、締固めの為にロードローラーで転圧します。
きれいに転圧されました。
さっきまでの砂利道が噓のように真っ平。
函渠の向こうから差し込む光は、工事の終わりを告げているようです。
もうじき竣工です!
足場の解体
いよいよこの時がきたのか...
長い間施工を共にしてきた足場を解体しています。
感傷的になってる場合ではございません、足場作業は危険と隣り合わせ。
ここで事故やトラブルが起きたら台無しです。慎重に慎重に...。
きれいさっぱり足場が解体されて私たちが作った函渠が姿をあらわしました。
竣工まであと少しです。
シュミットハンマー
せっかく作った管渠に穴をあけるのはやめてください!
と思ったらシュミットハンマーでコンクリートの圧縮強度を測定していました。
通常、コンクリートの圧縮強度を測ろうとすると、コンクリートを削ってサンプルを抜き取らなくてはなりませんが、
シュミットハンマーは内蔵のハンマーでコンクリートに打撃を加えて返ってきた衝撃の反射の強さで強度を測定します。
そう、物を壊さずに検査する非破壊検査というやつです。
簡単そうですって?とんでもない!測定箇所の選定とか、力の入れ方とか、角度とか、結構コツがいるんです。
カンタブ3兄弟
突然ですが、カンタブをご存じですか?
いいえ、ガンダムではありません。コンクリートの塩化含有量を測定する製品のことです。
なぜ塩分を測定するかといいますと、鉄筋腐食に影響を及ぼすので塩化物イオン量を把握するためです。
カンタブ3本を試料に差し込んでコンクリートに含まれる塩化物イオンの濃度を測定します。
塩化物イオンが存在すると中央の赤い部分が下からだんだんと白く変化するので境目の数値を読み取ります。
3本測定するのは3本の平均値を塩化物イオン濃度の測定値とするからです。
3本とも基準値以下で合格間違いなしです!
丸い模様の正体は
コンクリート打ちっぱなしの建物や壁などに謎の丸い模様がいくつもあるのを見たことはありませんか?
その丸い模様の正体はピーコン穴の跡です。
コンクリートを打設する際、型枠を固定させるためにプラスチックコーン(Pコン)を使用します。
コンクリートが固まって型枠を取り除くとピーコンの跡が穴になって残ります。
ピーコン穴をそのままにしておくと水が侵入し内部の鉄筋が錆びてしまうので充填材で埋めているのです。
綺麗に穴を埋めるのは作業員の腕の見せ所です。
現場に白蛇現る
新しい年が明けました。
今年も昨年同様、安全第一で工事を進めていこうと思います。
今日はやけに寒いと思ったら気温がマイナス4.5℃!?
気温が零度以下になるとコンクリートは凍結してしまいます。
凍結すると強度も耐久性も低下してしまうので、ブルーシートで覆い、ジェットヒーターで温めて養生する必要があります。
ジェットヒーターにビニールダクトを取り付けて養生する様子は大きな白い蛇のようですね。
今年は蛇年です。いい施工ができる予感がします。
年末年始に向けて
普段はなにかと騒々しい現場も、年末年始の準備を終えて静寂に包まれています。
年末年始は現場を閉鎖しますが、一般の方が間違って侵入してしまうと大変危険です。
立入禁止の防護柵を設置したり、三角コーンを置いたりすれば工事現場だと気づいて侵入することはないでしょう。
万が一侵入した場合、建設資材が崩れて怪我を負わせないよう現場の整理整頓も行いました。
また、停車中のトラックでも動いてしまうと事故を起こしてしまうので、タイヤストッパーをつけて動かないようにしました。
無事故で新しい年を迎えることができるよう、作業員一同願っております。
命を守るフルハーネス
大きな円形型枠の組立が完了しました!
だんだんと完成形がみえてきましたね。
ご覧の通り、みなさんフルハーネスを装着して慎重に作業をしています。
ジップラインする時とかよく装着しますよね。
工事現場でも、高所での作業の時は必ずフルハーネスを装着します。
早いもので、2024年がもうすぐ終わろうとしています。
怪我などしないよう十分に気を付けて新しい年を迎えたいですね。
インターンシップを実施しました
今日は現場がフレッシュでさわやかな空気に包まれています。
なんと、建設業に興味のある学生さんたちがインターンシップに参加してくれました。
施工中の現場を見学したり、VRで作業を疑似体験するなどにぎやかです。
作業員が説明すると、学生さんたちは真剣な表情で熱心に耳をかたむけてくれます。
まるで学生時代の自分を見ているようで懐かしい気持ちになりました。
いつか同じ現場で働けるといいな。
強い函渠をつくるために
函渠の型枠を組み立てています!
ついにここまできたかって感じです。
この工事では円形型枠というアーチ形の型枠を使用します。
この型枠にコンクリートを打設するとトンネルのようなアーチ形の函渠ができます。
この形は上、横、斜め全ての方向からの力を均等に受け止めるので強度が高いのです。
だからトンネルってアーチ形なんですね。
カラーマーク
鉄筋に黄色や緑色の色がついているのがお分かりでしょうか?
カラフルにして現場を明るくしようとしているのではございません。
鉄筋の径はロールマークで判断できますが、鋼種は見た目では区別できません。
識別カラー表(3枚目の写真)に基づいて、鋼種や径別に色分けしているのです。
色分けすればひと目で鉄筋を見分けることができて作業効率もアップ!
鉄筋の取り違えもなくなりトラブルも回避できます。
レイタンス処理
11月も半ばを過ぎてすっかり冷え込んできました。お鍋の恋しい季節ですね。
底版のコンクリート打設が終わり、レイタンス処理を行っています。
レイタンスとは、コンクリート打設後にセメントの微粒子や細かい骨材が浮き上がって上面に堆積してできる薄い層のことです。
お鍋に浮いた灰汁のようなものです。
これを放置したままコンクリートの打継を行うと、ひび割れが起こるなど強度に影響を及ぼす可能性があります。
ブラシでこすったり高圧洗浄機で吹き飛ばすなど、レイタンスの除去方法はさまざまですが、私たちのレイタンス処理の方法はひと味違います。
コンクリート表面にレイタンス処理剤を散布してレイタンスをコンクリート中に引き込み硬化します。
こうしてコンクリート表層部を強固にして完成度の高い打ち継ぎが可能になります。
鉄筋のロールマーク
鉄筋ってどれも同じでしょ、なんて思ってませんか?
実は鉄筋は種類によって強度が違うので使う場所も違ってきます。
でも、見た目が一緒で区別がつきませんよね。
鉄筋を見分ける際、私たちはロールマークを確認します。
写真では少し見にくいですが、鉄筋には赤い文字で径を表す数字と製造所のマークと強度を表す突起がついています。
これがロールマークです。汚れとかじゃないんですよ。
突起の数が多いほど強度も大きいんです。
ロールマークは鉄筋の取り違えによる施工ミスを防ぐためにとても重要なマークなのです!
コンクリートの検査
コンクリートを打設する前にコンクリートの検査をしています。
強度不足のコンクリート構造物ができあがってしまうと非常に危険だからです。
1枚目の写真はスランプ試験といって、コンクリートのやわらかさを調べます。
2枚目の写真はコンクリートの中に含まれる空気量を測定してます。
3枚目の写真はコンクリートの圧縮強度を調べるためのテストピースです。
後日、コンクリート圧縮試験機にかけて強度を測ります。
その他にも塩化物イオン濃度を測るなど、さまざまな検査をします。
安心・安全なコンクリート構造物を未来へ残す為、しっかりと検査をしています。
均しコンクリート
型枠を設置して均しコンクリートを打設します。
均しコンクリートは地盤面を水平にするとともに位置出しをする為だけに打設されるコンクリートです。
ですから、強度が必要ないので鉄筋も入れません。
別名「捨てコンクリート」なんて呼ばれてなんだか気の毒ですね。
しかし、均しコンクリートがなかったら地盤面はでこぼこで不安定です。
正確な位置出しもできないので施工精度は良くなりません。
強度の高いコンクリート構造物を作り上げるには、均しコンクリートは必要不可欠です!
基面整正をしています
暗渠を設置するためにバックホウで床掘りを行いました。
床掘をした後は、残った石などが浮いていたりして地面がデコボコしているので人力で整えます。
この工程を基面整正といいます。
ここに暗渠を設置するのですから、平坦で安定した基盤にする必要があります。
バックホウで豪快に掘って整えたあとは作業員がスコップで丁寧に地面を整えています。
平板載荷試験
10月に入りだんだんと秋が深まってまいりました。
現場周辺でも紅葉が見られるのでしょうか…楽しみです。
今日は平板載荷試験を行いました。
平板載荷試験とは、地盤を支える力(支持力)を現地で直接測定する試験です。
載荷板という直径30cmほどの円盤を地盤に設置し、パワーショベルで反力荷重を載荷板へ与え油圧ジャッキで段階的に荷重を与えて地盤の
支持力を調べます。
平板載荷試験は地盤に直接負荷をかけるので信頼性の高い試験なんです。
しかも、ボーリングなどの地盤調査に比べて騒音や振動が出にくく、近隣の皆様へ迷惑がかかりません。
結果は...合格です!
作業は順調に進んでいます。
騒音・振動対策
工事現場では大型車両が出入りしたり建設機械が動いたりするだけで騒音や振動が発生します。
やむを得ないことですが、近隣住民や通行人たちのストレスになるかもしれません。
とはいえ、騒音や振動を完全になくすことは不可能です。
さまざまな工夫をしてできるだけご迷惑をお掛けしないよう努力しております。
そのひとつが「表示板くん」です。
騒音計と振動計を内蔵しており、リアルタイムの騒音・振動の測定値をLEDパネルでデジタル表示します。
両方の計測値が一目でわかり、大きくてとても見やすいですね。
騒音、振動に対する意識を十分に高め作業してまいります。
岩盤の硬度測定試験
皆さん、ここで何をしているのでしょうか。化石の発掘でもしているのでしょうか...。
実は、岩盤の硬度測定試験をしています。
この試験は、岩盤を破壊することなく測定することができる非破壊試験です。
シュミットロックハンマーという機器を測定点に垂直に押し付けバネで打撃を与え、反発度を測定します。
また、計器が軽量なので、容易に多数の箇所で測定を行うことができます。
反発度はすぐに記録紙に印字されるので便利ですね。
バックホウの精度確認
ICT施工を行う前に、各工種や建機に応じた精度確認を厳密に行う必要があります。
精度確認とは、ICT建機(自動制御機能搭載の建設機械)が計測した3Dの位置データと、従来の測量機器(TSなど)で測ったデータがどれくらいズレているかをチェックすることです。
そのズレが、あらかじめ決められた許容範囲内に収まっているかを確認して、工事の正確さを確かめます。
今日はバックホウの精度確認を行いました。
バックホウの3次元座標は車内のモニターで確認できます。
精度確認を行うことで正確な施工履歴データを取得することができ、そのデータをそのまま出来形管理に使用することができるので、
これまで出来形管理作業に費やした多くの時間と労力を大幅に縮小できます。
バックホウの精度は合格でした!
ICTを活用して安心・安全で効率よい施工を行うためには精度確認は大切な工程ですね。
Geoスキャンを使って出来形確認
3次元計測技術を用いた出来形確認とは一体どんなことをしてるのでしょうか?
今回は盛土の出来形確認をご紹介します。
Geoスキャンとは、iPhoneとGNSSレシーバーが取得する位置情報を組み合わせて
「短時間で高精度な測量を行える」3次元測量アプリです。
測量というとドローンやレーザースキャナーを使って行う事もありますが、
今回は高額な機材や免許などが要らないGeoスキャンを使って測量をしました。
まずはアプリを使って測量したい領域をスマホで撮影していきます。
ちなみに測量のコツとしては、測量が終わると青く色が塗りつぶされるので
空間を塗りつぶしていく感覚で作業を進めていくと計測の抜けがなくなります!
次にポイントポイントでGNSSレシーバーを設置・画面をタップすることで標定点を追加登録します。(2枚目の写真がその様子です)
GNSSレシーバーの位置情報と3次元測量データが紐づけられるので、撮ってすぐに点群データが作成できます。早い!
そのデータをクラウド上にすぐアップロードをすれば遠隔でもリアルタイムで3次元測量データを確認出来ます。
他のアプリを使えば、このデータを使って表面積計算や測量データの編集解析まで作成する事も可能で、出来形検査までの作業時間が大幅に削減出来ます。
今までの出来形管理は基準高・法長・幅などを検尺テープなどで計測していたので、人と時間がとても必要でした。
そこにICTを導入すると、こんな風に人と時間を省略する事が出来ます。
今の建設業界は昔の3Kとは違います!働き方改革が加速していて、業務の効率化・短縮化が進んでいるんですよ!
ICT施工で転圧管理
1枚目の写真の車両は3DMC(3D Machine Contorol)ブルドーザーです。
3Dデータをもとに、重機の一部を自動でコントロールします。
ブレードの裏にセンサー、ブレードの上に乗っている黄色い棒のようなものはGNSSアンテナ、
運転席にはGNSS受信機等々が車両自体に装備されていて、ブレードの高さ位置・勾配を自動でコントロールして作業を進めてくれます。
このシステムを使うと、ブレードの動きを設計値に合わせてコントロールするため丁張りを削減できたり、
重機を止めて丁張りを確認する事が不要なので、作業の効率がとても上がります!(私のテンションも上がります!)
オペレーターの熟練度によって品質に差が出にくいので、若手・ベテランに関わらず安定した品質を確保する事ができます。
そして2枚目の写真は締固め回数分布図を確認しているところです。
今回の現場では位置計測装置(TSやGNSSなど)を使って転圧回数と走行軌跡を管理する「転圧管理システム」を導入しています。
具体的には、締固め車両の走行軌跡を計測・締固め回数をリアルタイムにオペレーター画面に表示することで締固め不足の防止と均一な施工のサポートをしてくれます!
施工範囲をメッシュに分割し締固め回数がリアルタイムで色分け表示されます。(写真は4回締固めしたので、赤色になっていますね)
また、施工結果のデータは帳票作成するソフトで自動作成もしてくれるので書類を作成する手間もありません!
この様に現場では業務の効率化が進むICTが欠かせない存在になっています。
大型土のうの作り方
9月に入ってもまだ暑い日が続きますが、高く澄みきった空は秋の気配を感じます。
今日は大型土のうを作ります。ひとつで2トンほどの重さがある大きな土のうです。
そんなに重いものをどうやって製作・設置するのでしょうか。早速見てみましょう。
バックホウが吊り上げているのは瞬作という土のう製作治具。じょうごの形状になっています。
瞬作に土のう袋を履かせてバックホウで土砂を入れます。
あとは瞬作を吊り上げて袋から抜いたら完成。
瞬作の登場で作業効率が格段に良く、安全に作業できるようになりました。
社内安全パトロール
今日は社内安全パトロールを実施しました。
労働災害を未然に防ぐために月に1度、責任者及び担当者が現場内を巡回します。
事故につながるような危険な箇所を発見した場合は、ただちに作業方法の見直しや機械設備の修理・メンテナンスを行い労働災害を防止します。
他にも、整理整頓がなされているか、各職種間で連絡調整ができているかなどもチェックしています。
幸い是正が必要な指摘はなくホットひと安心。
毎月実施される社内安全パトロールは、私たち作業員の安全に対する意識を向上させてくれます。
ジオテキスタイルの敷設
毎日暑い日が続いておりますが、皆様体調はいかがでしょうか?
夏期休暇中はゆっくりと体を休めることができ、心身ともにリフレッシュすることができました。
しっかり充電できたところで、これまで以上に安全第一で作業してまいります。
写真は仮置場にジオテキスタイルを敷いている様子です。
ジオテキスタイルとは、合成高分子材料を用いて作られた土質安定用の繊維製品で、主に土の補強などに使用されます。
幅4.9m、長さ100mもあるので、クレーン車で運びます。
ジオテキスタイルの重ね幅は決められた幅になるよう丁寧に敷いています。
一番右の写真が敷設完了の写真です。ジオテキスタイルが真っ白なのでまるで雪景色のようですね。
綺麗に敷くことができました。
少しもったいないですが、この上に盛土をして軟弱地盤を補強します。
災害防止協議会による巡視
8月の災害防止協議会による巡視が行われました。
災害防止協議会は、建設現場での労働災害を防止する為に運営される組織で、月に一回開催されます。
現場の巡視はその活動のひとつで、安全な作業環境を確保するために行います。
現場内に危険な箇所はないか、重機や機械などの設備は安全か、整理・整頓や清掃がなされているかも確認します。
巡視が終わったら現場事務所に戻って話し合い、危険な状態や不備があれば改善策を提案します。
こうした取り組みにより建設現場の安全性は向上しているのですね。
今回は特に大きな指摘もなく無事に巡視が終了しました。
協議会の皆さま、猛暑の中ありがとうございました!
私たちの熱中症対策
毎日暑いですね。ここ数年の夏は猛暑が常態化しているようです。
今年もすでに記録的猛暑となっております。
夏の工事現場では、熱中症による労働災害を防止することが重要です。
弊社もいろいろな熱中症対策グッズを取り揃えておりまが一部をご紹介しますね。
左1枚目の写真はクエン酸たっぷりのフルーツキャンディ。おいしく熱中症対策できます。
右2枚目の写真は熱中症キット。備蓄水が2本とパンチして瞬間冷却する冷却剤が4つ、ポータブルソルトが収納バックに入ってます。
これがあればもしもの時に応急処置ができますね。
作業員を熱中症から守るのはグッズだけではありません。
熱中症を予防する為の知識が必要です。
尿の色で脱水症(熱中症)か否かをチェックできます。体内の水分が不足すると尿の色は濃くなるんですね。
左3枚目の写真は尿チェックシートです。トイレの前に貼ってあります。
チェックシートを見てからトイレに入りましょう。
右4枚目の写真は暑さ指数(WBGT)測定器と熱中症注意喚起看板です。
暑さ指数とは単なる気温ではございません。気温と湿度と輻射熱の3つを取り入れた指数です。
こまめにチェックして水分や休息をとるようにしています。
ドローンでICT測量
私たちは今ドローンで起工測量しています。
ドローンで上空から測量現場を撮影し、その写真画像を元に地形の三次元データを作成します。
三次元データはソフトウェア内でほぼ自動で作成されます。なんて便利なんでしょう。
これまでに測量に要した膨大な時間は何だったんだ、と思うほど、短時間で測量は完了します。
また、少ない人数で測量できるため人件費の削減にもなります。
このように、ドローンの登場は工事現場に大きな変化をもたらしました。
もはやドローンは私たちにとって新しい建設機器と言っても過言ではないでしょう。
いよいよ工事が始まります
はじめまして。この度、本工事の施工状況などを日々発信することとなりました。
私はまだ若手ですが、先輩達の巧みな技術なども合わせてご紹介していきたいと思います。
さて、工事に入る前に工事看板を設置しました。
工事の内容や期間・時間帯をシンプルで分かりやすく表示しました。
また、本工事では週休2日制適用工事となっていて、その背景や目的なども表示しています。
工事現場は昔と比べるととても働きやすい職場環境になりました。
週に2日間休めるのでリフレッシュした状態で仕事に取り組めますね。
工事現場で働いてみたいという方、是非一緒に働きましょう!
現場事務所も設置しました。工事の準備が着々と進んでいます。